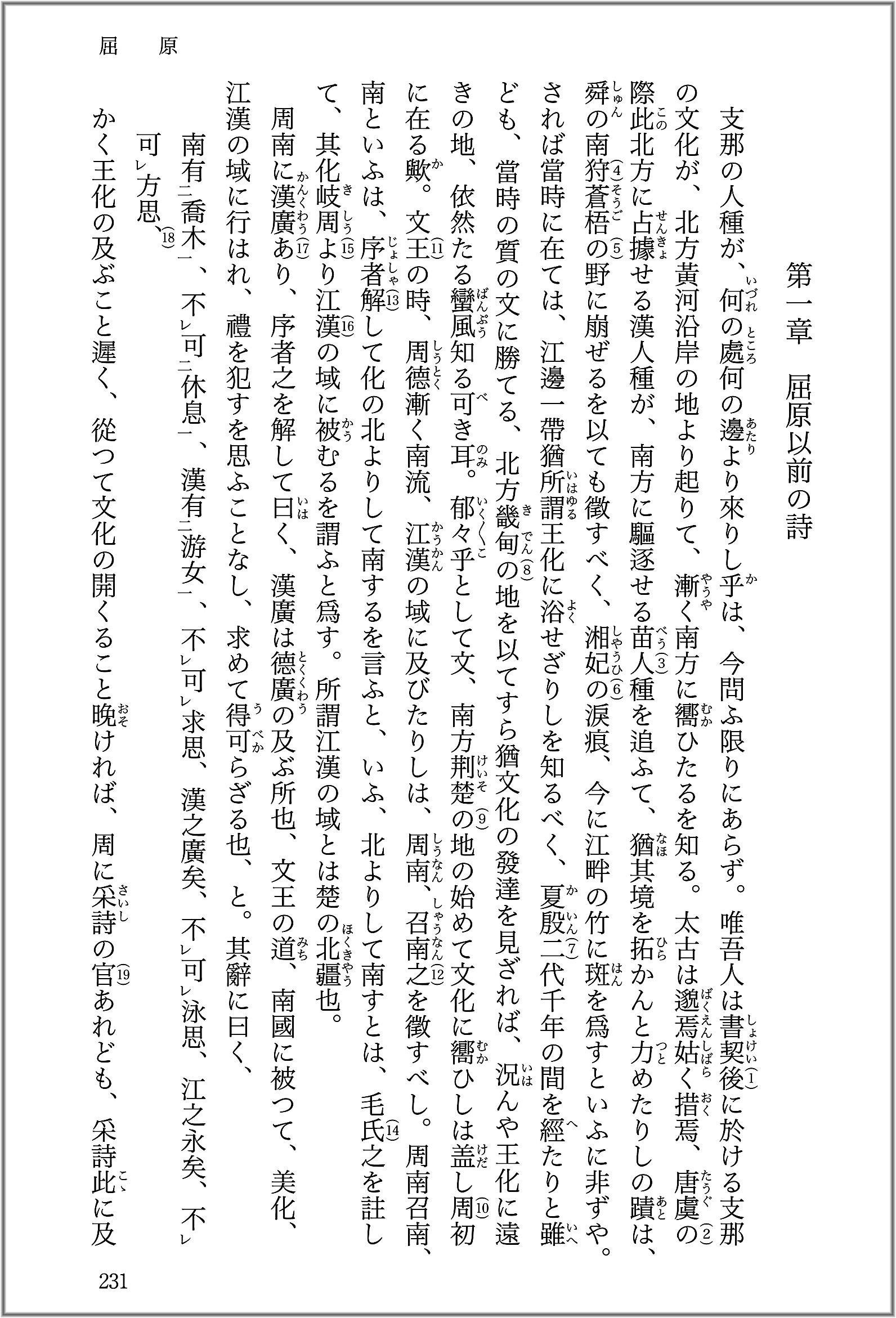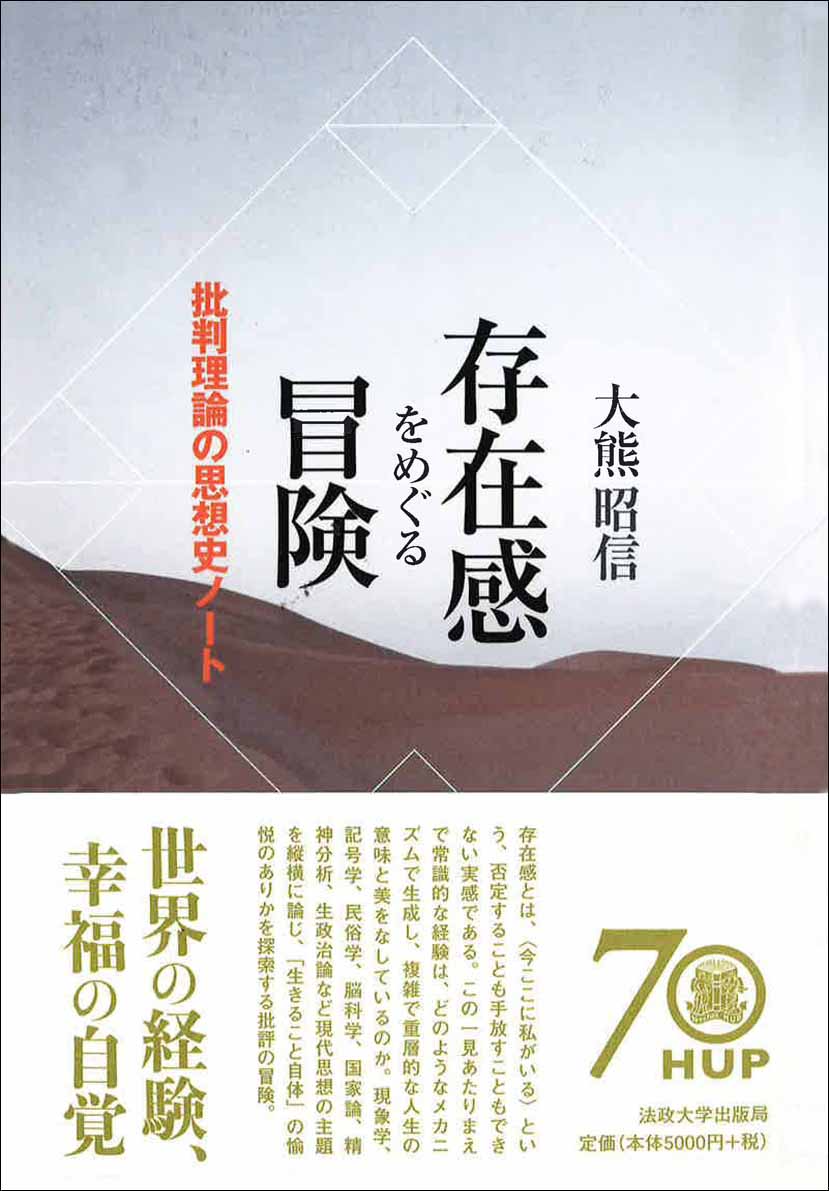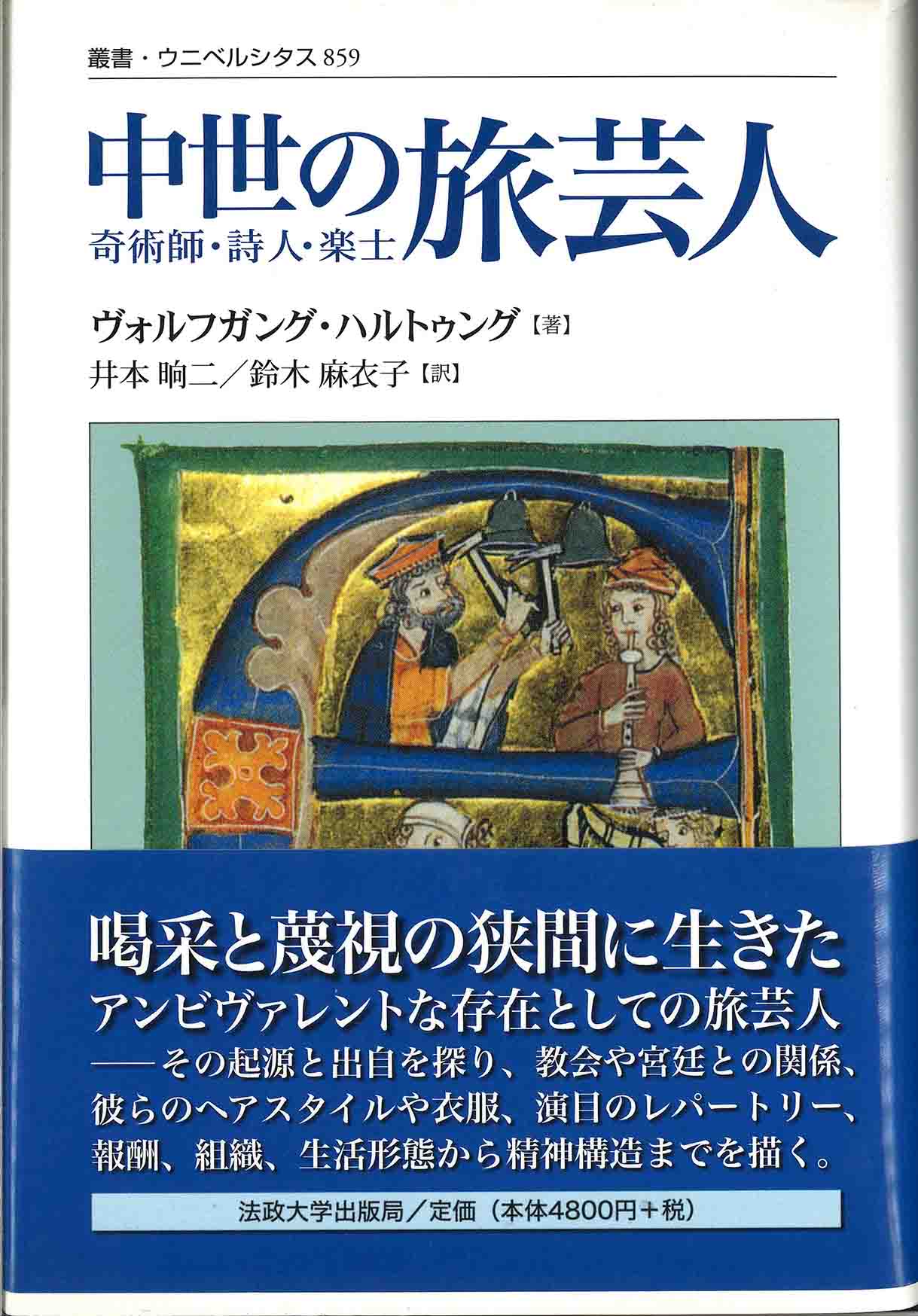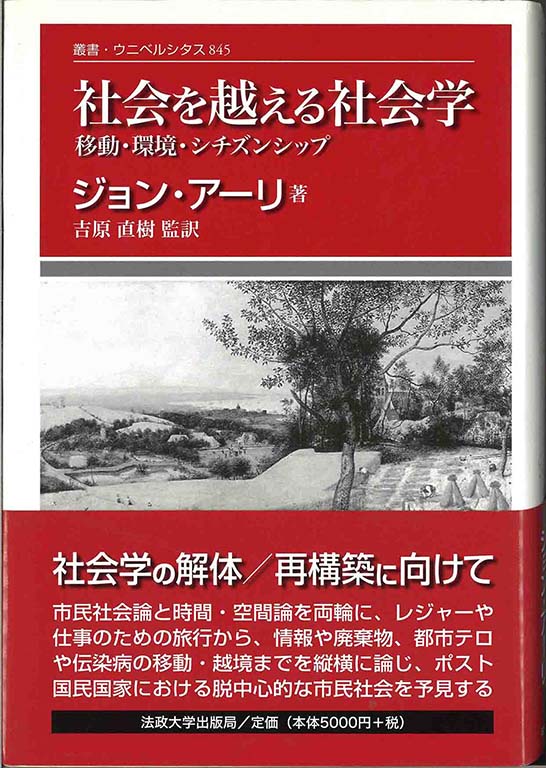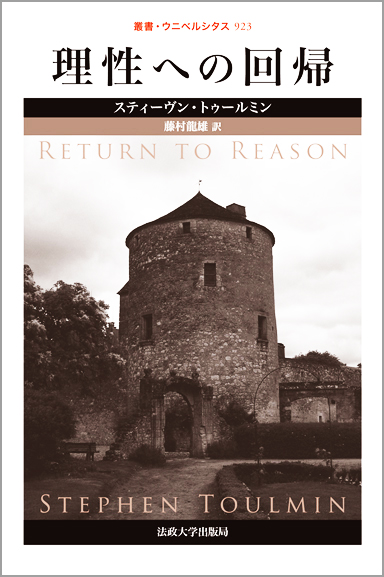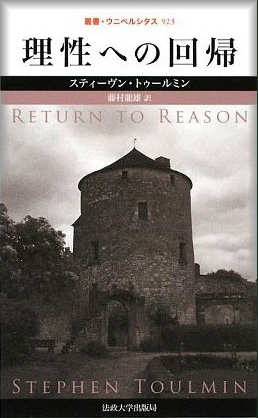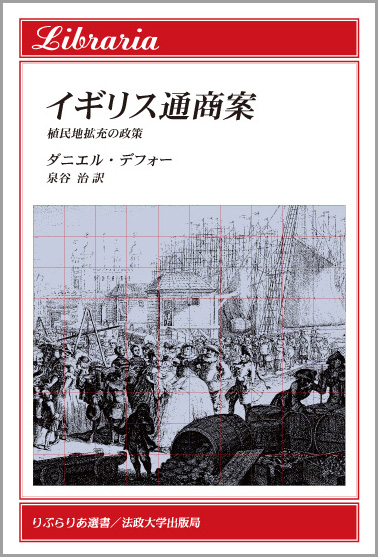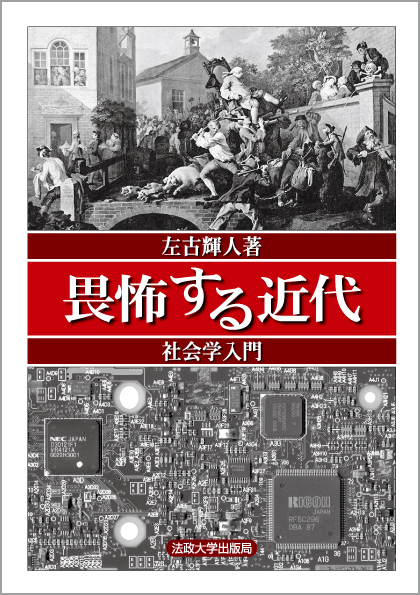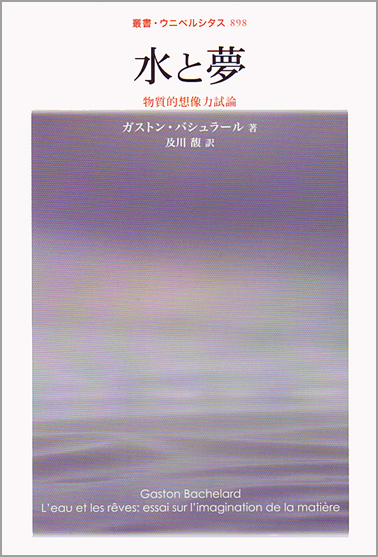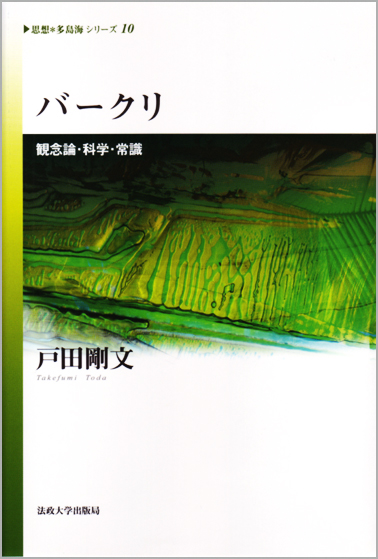文字を「組む」というコト
原書は、大日本図書株式会社が刊行した「支那文学大綱」である。ネットで書影を見ることができるが、経年劣化しているものが多く、ほとんどの図書館で現物を複写することは困難であった。国立国会図書館のウェブサイトで閲覧することのできるデジタルコレクションでも、解像度の低いものばかり。活字をデータ化するために現物を撮影して作られたマイクロフィッシュを入手するところから始めた。
今回の物は刊行年が明治30年代(1890年代)のもの。いわゆる電算写植が普及しだすのは1960年代だと思われる。それに先立つこと70年も前のもの。当時、どのように印刷していたかは実際に見ていないが、今より手間も暇も掛かっているのだろう。現代ではコンピューター上で行える文字の統一も、手作業で追いながら拾ったのだろう。宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」では、主人公のジョバンニが印刷屋で活字を拾う(文選)アルバイトをするシーンがあるが、おそらく今回のものもそういった気の遠くなるような作業がなされていたはず。
当社での翻刻の仕事は戦後のものがほとんどである。絶版になった本を、改題などを付け加えて別の出版社で出版する。テキストデータがあればベストだが、もらえない場合もある。その場合でも、現物が手に入れば文字入力に苦労することはない。印刷状態がよければ、OCRを使用することが出来る。
だが書物を構成する文字は戦前の物である。OCRの識字率は向上しているが、試しにOCRを掛けてみたところ、識字率は50%以下であった。100年以上前の書物であること(印刷文字が滲んだり、掠れたりしている)や、旧字体であることが原因。また、嶺雲が原典から写し間違えた文字、植字上の誤りなどが混在していた(偏旁冠脚が逆になっているものなど)。さらに文字の統一も手作業での校正ゆえに完全ではなかった(例えば、「真」と「眞」、「即」と「卽」などの混在)。
結局のところ、人力で入力した方が効率的である、という結論に達した。この書物が編まれた時と同様に、文字を掬い取っては入力していく。職人たちも嶺雲が手書きした原稿を受け取り、文字を一つ一つ拾っては植えていったのだろう。春に種蒔きするように。
現代では著者から手書き原稿を受け取ることはあまりない。ほとんどデータ入稿である。今回の作業は明治期の職人たちが行っていた作業量にはほど遠い。また蒔かれた種をうまく受け渡せたかは分からない。だが往事の職人たちの息づかいを微かに感じることができた。